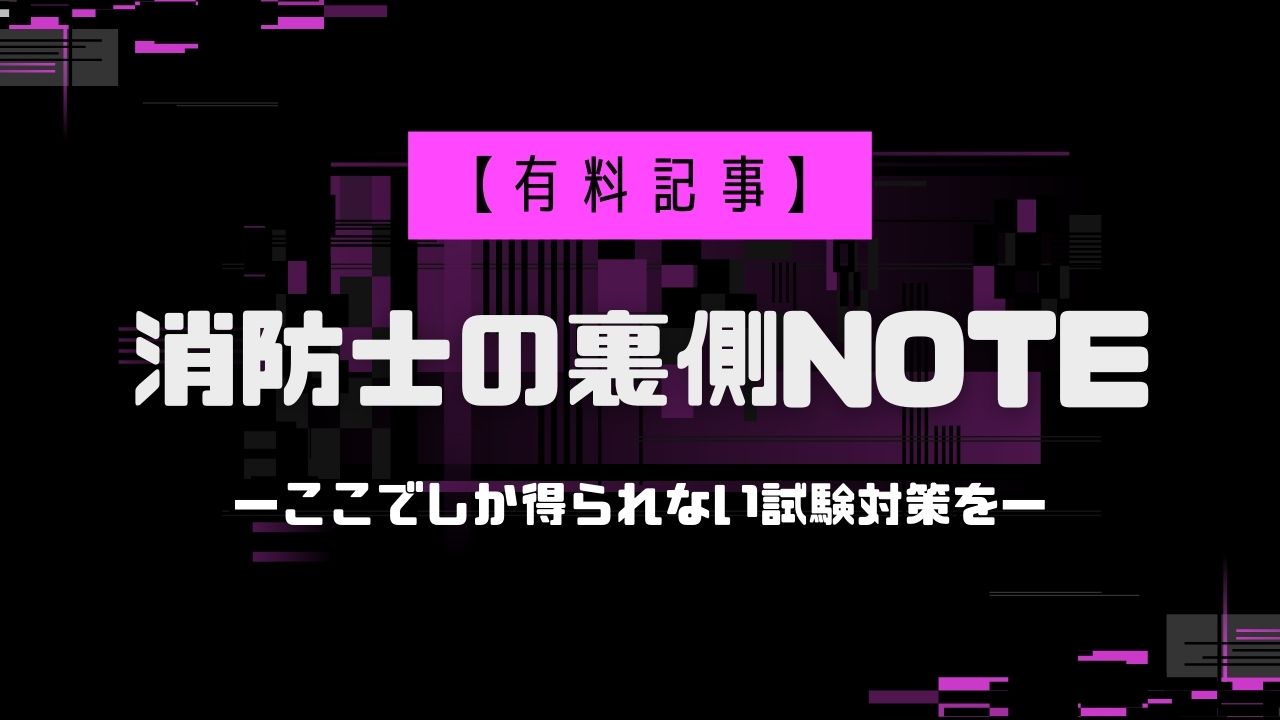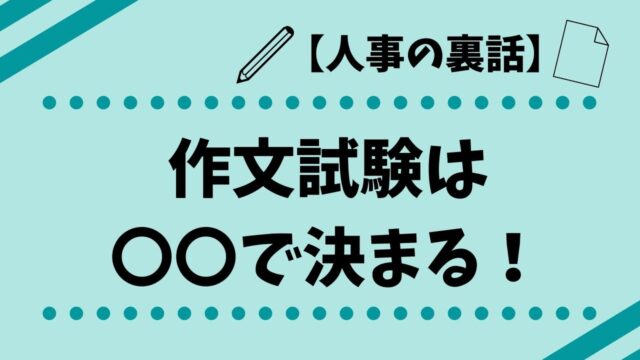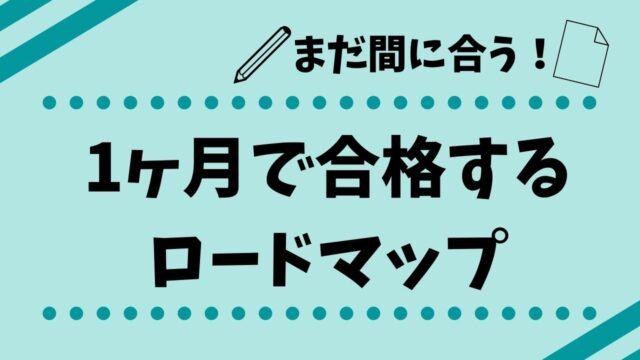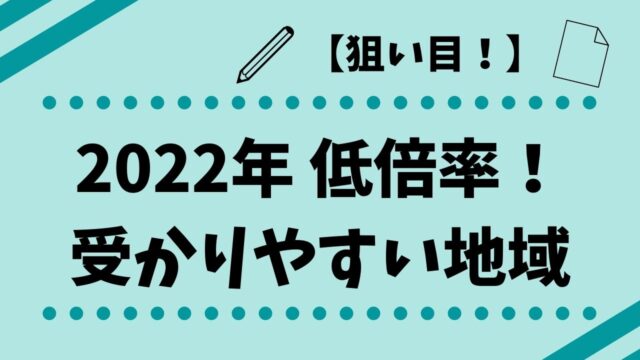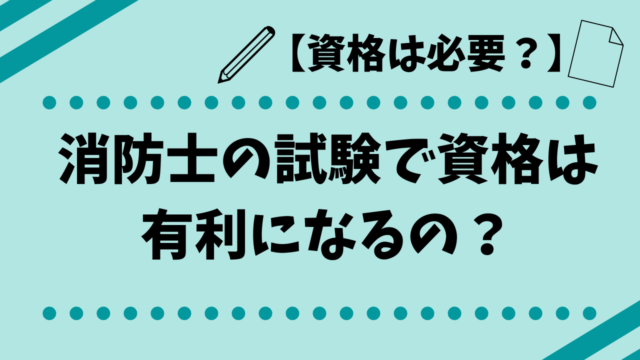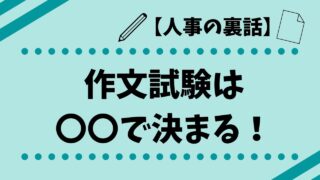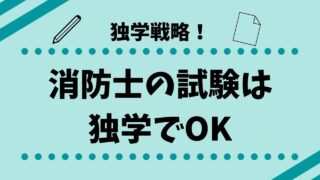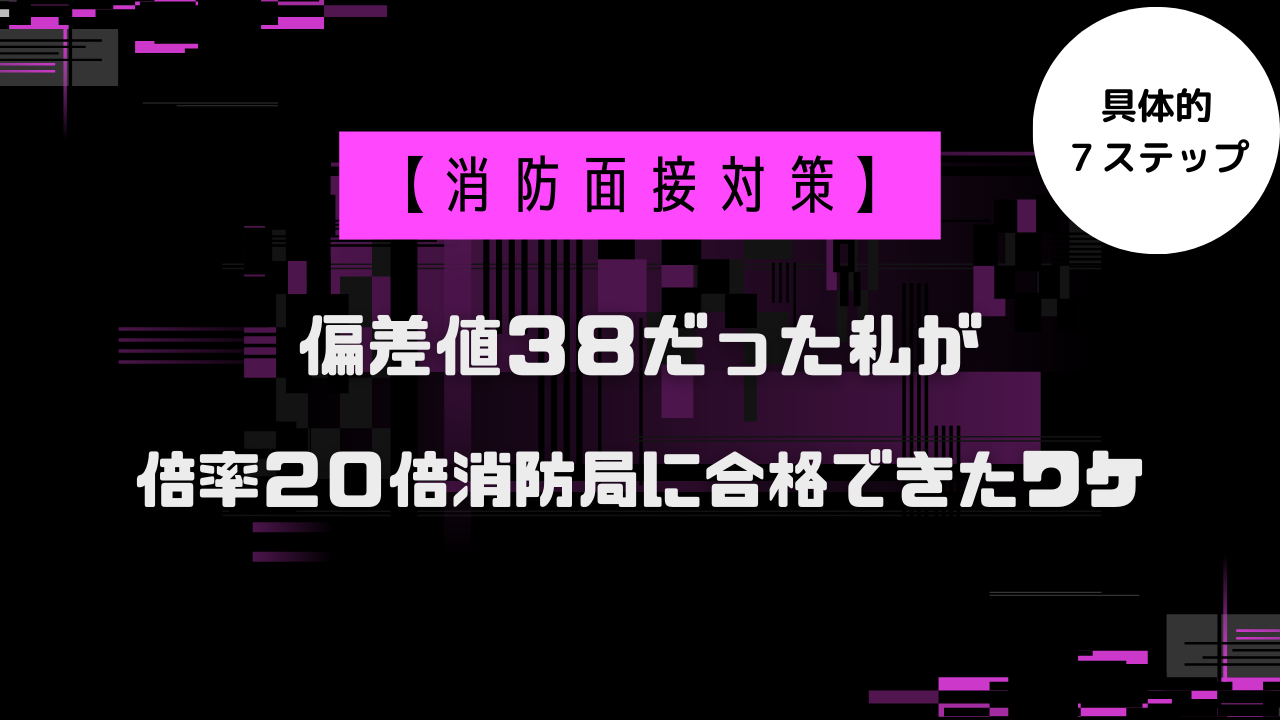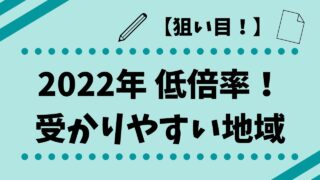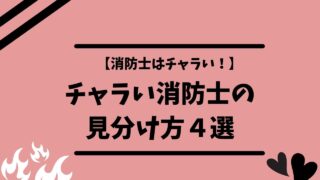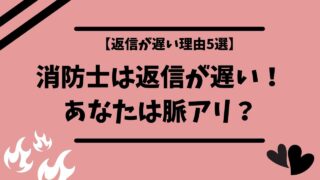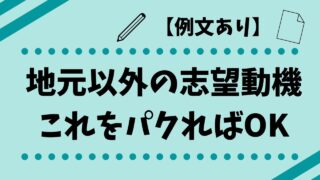今回はこんな疑問を持つ方へ向けての記事となります。
筆者のプロフィール
・元消防士で現在はフリーランス
・Fラン大から倍率20倍消防局に合格
・公務員試験には3回合格してます
なので消防士の試験対策には精通していますので、それなりに参考になる情報を発信できると思います。
本記事を読むことで…
消防士の作文試験で困らなくなる「消防ネタ」と「テンプレ文」を知ることができます。
この記事の内容は以下の通りです
・作文試験で使える消防ネタ4つ
・作文試験で使えるテンプレ文
・テーマ別で使うべきテンプレ文
まず始めにこの記事を読むポイントです!
・テーマを決めて作ったものではありません
・各パートを組み合わせるのがオススメ
・ご自身で作られたパートと組み合わせてもOK
・基本的に例文の丸パクリもOKです
それでは詳しく解説していきます!
【パクってOK】消防ネタとテンプレ文4選
①家具類の転倒・落下防止対策の実施率は57.3%
・令和2年の東京消防庁による調査
・転倒、落下防止対策率は57.3%
・この値は直近7年間で最も低い
・理由は「面倒」「場所がない」が多い
・しかし震災等により防災意識は上昇傾向
令和2年度の東京消防庁の調査によると、家具類の転倒・落下防止対策を実施している世帯は、57.3%であった。震災が頻繁に起こる近年、国民の防災意識は上昇傾向であるが、この57.3%という値は直近7年間で最も低い値だ。対策を実施しない理由として「面倒だから」、「防止対策をするスペース(場所)がない」などが多く挙げられた。これらの打開案として、消防主催のイベントの開催が有効であると考える。
イベントの具体的な内容は、起震車を用いて実際の揺れの強さを知ってもらったり、中途半端な落下対策では危険は防げないということを身をもって体験してもらう。実際に現職の職員と触れ合うことで、具体的なイメージが湧くのではないだろうか。また「防災グッズはこれさえあれば大丈夫」というような名目で具体的な防災グッズを展示し、防災対策のイメージを深めてもらうのだ。防災グッズに関してはゲルで家具の脚を固定するものや、手軽に壁に貼り付けられるベルトタイプの固定用品など、一昔前とは違い場所を取らずに安全に落下対策ができる商品が販売されている。こういった新しい情報や、意外と手間がかからないという実状を知ってもらうことが重要だ。災害を経験した機会が少なく、災害に対する危機意識が低いことが防災意識の低下に繋がっていると考える。そのような層に向けて消防イベントの積極的な開催は効果的である。
消防イベントをより多くの市民に参加していただくには、日ごろの行いを通して市民と信頼関係を築き、防災に興味を持ってくれることが大切だ。例えば、現場活動や署見学に来てくれた親子の方へ精一杯のサービスを施す努力をする。こういったことを日ごろから心がけ、私は接遇日本一の消防官を目指したい。そして市民の信頼を得て組織に貢献し…。
②公務員倫理の確立が求められている
・公務員の不祥事が相次いでいる
・令和元年の地方公務員の懲戒処分者は4244人
・倫理観の欠如や希薄化が指摘されている
・職場環境や職員の精神面が原因とされる
近年、公務員の不祥事が相次いで発生し市民の信頼を大きく損ねるような重大な違反が続いている。令和元年の総務省調べによると、令和元年中に懲戒処分に付された者は4244人で、昨年と比較し63人の増加となった。行為別でみると服務違反関連の名目が最も多く、その数は年間懲戒処分者数の約4割を占めている。これは倫理観の欠如や希薄化が原因となって起こるとされており、自治体の中には公務員倫理委員会なるものの設立や、倫理研修、ディスカッションの場を設けている場所も増えてきた。また消防官も地方公務員の位置づけであるため、この問題は対岸の火事ではない。特に消防官は過酷な現場活動、失敗が許されないプレッシャーのかかる場面など、職員が受けるストレスは精神的・肉体的ともに大きいものである。そうなると行政職などよりも、より一層「職場の風通しのよさ」を追求していく必要があるだろう。
私は消防官の不祥事を未然に防ぐためには、職員間の密な対話や積極的なコミュニケーションが重要であると考える。不祥事を起こしてしまう職員は精神的に不安定な状況であったり、職場に馴染めないなど職員間の風通しの悪さが起因するものが多いとされる。そのため積極的なコミュニケーションを取ることで、各職員の価値観や考え、悩みなどを共有することができ、お互いが助言や手助けをしやすい環境を作ることができる。
私は「細かな部分に気付ける」消防官を目指す。日々の訓練や現場活動、日常業務でも大枠だけでなく細部に目を向けることで、新たな発見を得て日々成長していきたい。具体的には資器材の点検や取扱時にも指差し呼称を抜かりなく行うなど、一つ一つ当たり前の確認行為をないがしろにしないよう心がける。そして日常的なそのような視点は、観察力や注意力の向上にもつながると考える。この力を磨き上げることで、職員のコンディションや考えを把握しやすくなり、円滑なコミュニケーションを取ることができる。細かい部分に気付くことで、風通しの良い職場を実現させることが不祥事の防止に繋がり…
③救急出動件数はここ20年で約1.6倍増加
・原因は高齢化に伴う傷病者の増加
・出動件数と搬送件数は違う
・未搬送事案が年間約50万件以上発生
・軽度症状件数は実に全出動の約7割
・救急車の適正利用が叫ばれている
・救急安心センター(♯7119)の重要性
・全国18地域で実施されている
・12年間で5%の軽症者搬送削減
救急車の出動件数は年々増加傾向にあり、平成12年と比較し令和元年現在では約1.6倍に増加している。これの最たる原因は、高齢化に伴い救急車を要請する高齢者が増えているためである。しかし実際には、救急車を要請しても傷病者が軽症のため未搬送となる事案も多く、その件数は年間50万件を超えている。この件数は実に、救急出動総数の7割を超えており、現在救急車の適正利用が叫ばれている。救急車の車両が不足すると、本当に救急車を必要としている市民が手遅れとなってしまったり、事案に対応しきれないなど市民サービスの低下を招くことになる。
このような問題の対策として有効なものは、救急安心センター事業の周知と促進である。このサービスは簡単に言うと、通報者が本当に救急車を必要とするかどうかを判断してくれる受付窓口である。このサービスを実施している自治体は全国に18地域あり、東京消防庁調べでは実際に12年間で約5%の軽症者搬送の削減に成功している。とはいえ令和2年現在、救急安心センターを実施している地域はまだまだ少ないのが現状だ。そもそもこのサービスを知らないという一般人も数多いだろう。そのため救急安心センター事業を世の中にどうやって浸透させていくかという観点で考えていく必要がある。
私はこのサービスを普及させるために、消防本部公式のSNSを利用した情報発信を提案する。現代のSNS普及率は非常に高く、情報の拡散には大きく役立つ時代となった。しかし、ただ情報発信するだけでは十分な周知には至らない。したがって、まずは市民が住む町と消防行政に興味を持ってもらうことが必要だ。私は市民から関心を得てもらうために、常に小さなことを大切にするような消防官を目指したい。市民に対しての挨拶や接遇、気づかいなど細かな部分に目を配り、市民から「あの消防士さんは立派だ」と思われるよう心がけたい。そしてそういった職員が増えるよう自ら働きかけ、〇〇消防本部のイメージアップを図ることで…
④多様化する災害と人工知能について
・通信技術の発展は消防にも影響あり
・ドローン操作などの研修も開始
・現場映像を送信する「Live119」の促進
・AI必須の時代になりつつある
近年のICT(情報通信技術)の発展は著しく、多方面に画期的な効率性をもたらしている。消防も例外ではなく、最近では現場映像を119番指令室に送信する「Live119」システムの登場や、ドローンを用いた操縦研修の実施など消防行政のAI化が進んでいる。自然災害が多様化する現代、このような情報通信技術の力は消防にとって必須の時代がやって来る。例えば災害が起こった時、AIが瞬時に被災状況や避難経路のデータを本庁に転送し、被災地域の状況や、災害を予測して被災人数を最小限にとどめるような技術は有事の際の被災者削減に大きく役立つ。またインターネットが普及した現在、情報の発信・周知にも追い風が吹いており、特にSNSを活用した広報などは一般市民の防災意識を高める手助けとなる。
総務省が公表した調査によると令和2年の国内SNS利用率は73.8%であり、これからの時代は消防主催のイベントや講習を通したアナログな広報よりも、Twitter等のSNS媒体を用いた情報発信が肝になると考える。またSNSを通してより多くの市民に情報を共有してもらうことで、「自助」の側面からも防災意識の向上に繋がるだろう。具体的には防災グッズの紹介や過去の災害の事例や問題点を発信することで、災害が起こった際に取るべき行動のイメージが付きやすくなると考える。
私は消防本部公式のSNSをより多くの市民に見てもらうために、まず消防の基礎業務を身に付け、将来的には各種消防行政のPRや様々な企画を立案できる部署を目指したい。またマーケティングや集客について学び、様々なSNS媒体での発信を通して多くの方に○○消防本部を知ってもらうような、市民との橋渡しができる消防職員になることが目標だ。そこで防災知識や応急処置等の情報を発信し、市民の防災意識と共助の力を高まることで市内の安全性を向上させていきたい。このような形で私は組織に貢献し…
【テーマ別】このテーマにはどの型が使える?
「少子高齢化」関連のテーマにはコレ
・③のパート1~結論
また「④パート1」のLive119システムを深く掘り下げて、周知と普及の側面から高齢者削減へアプローチしても良いでしょう。
「自然災害の問題点と対策」関連のテーマにはコレ
・①パート1~結論
・④パート2~結論
「理想の消防士」「消防士に求められるもの」関連のテーマはコレ
・②パート2~結論
要所要所で切り抜いて、閲覧者様の素直な気持ちで書いて繋げても大丈夫です。
【消防士の作文試験】テーマと消防ネタまとめ
・文章の「型」を覚えれば時短可能
・ポイントを押さえれば丸暗記は不必要
・テーマごとにどの型が使えるか見分けることが重要
いかがだったでしょうか?
作文試験が苦手な方にとって参考なれば幸いです。
作文試験は1から考えようとするから大変なんですよね。
なので「このテーマにはこの型が使えるな」というような感覚を身に付ければ、大体のテーマには対応できてしまいます。
作文試験では、テーマに合わせてどの型が使えるかを抜き出す訓練をして、できるだけ多くの時間を推敲にあてられるよう対策することが有効ですね。
本記事は以上となります!